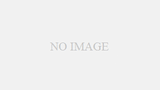※この記事は2019年8月21日に「はてなブログ」に掲載した記事を転載したものです。
オーダーメイド集計というものがある。
オーダーメード集計とは、既存の統計調査で得られた調査票データを活用して、調査実施機関等が申出者からの委託を受けて、そのオーダーに基づいた新たな統計を集計・作成し、提供するものです。
統計局ホームページ/オーダーメード集計の利用
簡単に言うと、既存の統計調査ではわからなかったことがわかるようになるということだ。研究の幅が広がる。素晴らしい。
私もオーダーメイド集計を利用した調査を行ってみたい。ただ何をどうすれば良いのかわからない。ということで、まずは統計センターの説明。
あとは実際にオーダーメイド集計を利用した論文を参照した方が分かりやすいだろう、ということで2論文の紹介。
・髙谷幸ほか(2015)「2010年国勢調査にみる外国人の教育 : 外国人青少年の家庭背景・進学・結婚」『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要』39, 37-56
CiNii 論文 – 2010年国勢調査にみる外国人の教育 : 外国人青少年の家庭背景・進学・結婚
・髙谷幸(2019)「現代日本における移民の編入様式 : 家族を通じた分岐とジェンダー構造」『大原社会問題研究所雑誌』729, 65-89 ※大原社会問題研究所HPにフルペーパーあり
CiNii 論文 – 現代日本における移民の編入様式 : 家族を通じた分岐とジェンダー構造
色々調べてみたが大きな問題が2点あった。
①費用の問題
オーダーメイド集計は自分ではできない。統計センターや各省庁が代わりに行う。その際、1時間当たり4400円の費用が発生する。奨学金で研究している身。この費用負担は厳しい。
②利用可能なデータの制限
すべての統計調査でオーダーメイド集計ができるわけではない。私は生活保護に関するオーダーメイド集計を行ってみたい。生活保護に関する統計調査として代表的なものは、厚生労働省が行っている「被保護者調査」だ。そして、なんと本調査はオーダーメイド集計の対象に入っていない…!なんてことだ。極めて残念…。

オーダーメード集計の利用 | ミクロデータ利用ポータルサイト
しかし、何としてでもオーダーメイド集計を利用したい。私はあまり優秀とは言えない大学院生だ。「底辺研究者」としてやれることはやる。しぶとさで勝負だ。
一縷の望みをかけて関係機関に問い合わせてみる。その結果はまた報告します。